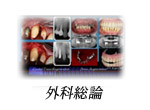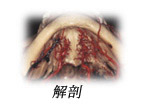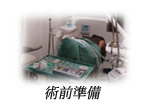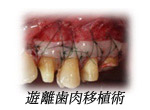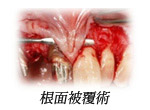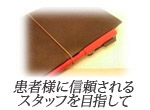SBCの「これまで」と
「これから」
- 歯周形成外科コース(SBC) HOME
- SBCの「これまで」と「これから」
現場ですぐに実践できる歯周治療の
基礎をお教えいたします

たとえば、長持ちするインプラント治療を行う場合、口腔内全体の歯周病の有無や進行状態などをしっかり把握しておく必要があります。しかし歯科医療現場では歯周治療の知識・経験の不足から適切な診断および処置が行えずに治療が失敗してしまうケースも報告されています。

あおいデンタルクリニック院長(SBC代表)の青井はこのような歯科医療現場の問題を解消するため、「基礎がしっかりできている歯科医師を育てること=日本の歯科医療の底上げになる」と考えました。そして、この考えに賛同した歯科医師と歯科衛生士と共に起ち上げたのが全国の歯科医師やスタッフ(歯科衛生士・歯科助手)を対象にした歯周形成外科コース「SBC(Surgical Basic Course)」(以下SBC)です。
SBCの目的
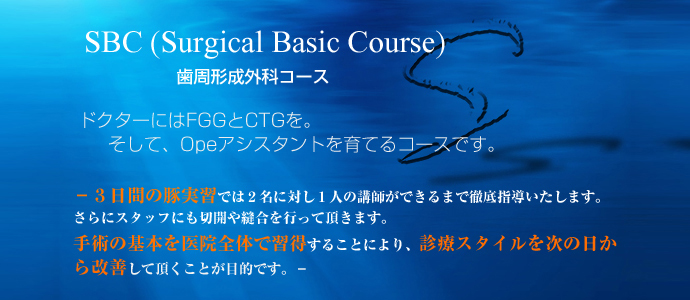
講習内容
|
近年、インプラントなど外科術式が複雑になり、情報が混濁しております。基本に立ち返り、外科手技を学びましょう。 |
各回、午後は豚顎を使った実習があります。「聴いて」「見て」「自分で行う」ことで理解できるよう、参加型の講習会となっております。 |
口腔周囲の血管・神経系・組織隙などの解剖学を習得することで、手術の偶発症を極力避けることができます。 |
|
歯周治療の3本柱である、「原因の除去」「環境の改善」「メンテナンス」と、骨欠損状態に応じた治療計画の立案方法をご紹介いたします。 |
適切な術前準備(口腔内消毒・滅菌・器具出し・ドレーピングなど)は処置成功への第一歩です。 |
アシスタントワーク(排除の仕方や外科バキュームの位置など)や、患者様のメンタル部分のサポートについてお話しします。 |
|
すべての手術の基本である切開、剥離、縫合。基本テクニックをマスターすることによって、予知性のある処置が行えます。 |
外科器具はそれぞれの用途があります。器具の特徴や正しい使い方を覚え、使いこなせるようになるための知識を習得できます。 |
清掃性が高く長期的に安定した口腔内環境に改善するために必要な角化歯肉を獲得する手技を習得できます。 |
|
歯肉退縮によって起こった根面露出の診査・診断、術式の選択など、様々なケースを診て、実践できるようになります。 |
ストレスなく確実な手術を行うためには、外科器具のシャープニング、メンテナンスは必要不可欠です。各回実習も行います。 |
手術を成功させるためにもっとも重要なことは、医院と患者様との信頼関係を築くことです。接遇マナーや応対のポイントをお話しします。 |
SBC講義風景
SBC設立の経緯と
我々の考え

こんにちは、SBC代表の青井です。
受講生一人ひとりに行き届いた講義をしたいという思いからスタディグループの設立を決意しました。
はじめは一人で起ち上げる予定でしたが、これまでにつながったインストラクターの先生や受講生に講習の目的やカリキュラム、講義の仕方などを話したところ、数名から賛同を得られましたので、そのメンバーとともにスタディグループを発足することにしました。インストラクターの人数は受講生とほぼ同じにし、受講生一人ひとりに細かいところまで教えられる体制を整備。また、インストラクターを増やすことで休みをとりやすくし、休日を利用して他のスタディグループの講義やセミナーを受けられるようにしました。
技術よりも知識が先にあるべき

私が大切にしている考えのひとつに、「知識あっての技術」というものがあります。著名なドクターや歴史あるスタディグループでは素晴らしい講義がたくさん開催されていますが、インストラクターに成りたての頃は成功症例の紹介に留まり、治療の基礎となる考え方やメカニズムなどがわかりにくい講義をしていたように思います。講義後に「あの先生と同じようにやってみよう」と実践しようとしても、結局根本である基礎が理解できていないため、同じようにはできないのです。そこで、私は以前から歯科治療のなかでも特に重要性を感じていた歯周形成外科の基礎の習得を目的とした「SBC(Surgical Basic Course)」を作りました。
基礎(ベーシック)を押さえて歯科界のボトムアップに貢献したい

SBC設立当時は、歯周形成外科のベーシックを軸にしたスタディグループがなかったため、私は今まで行った講義や資料をまとめ文献などを参考にしつつ、そこにSBC独自のカリキュラムを加えて講習内容を組み立てました。
たとえば、予後の良い切開方法を教える際には、器具(メス)の引き方はもちろん、0.5mmズレるとなぜ治癒が遅くなるのか?といったメカニズム(理由)を教えるなど、根本的なことをしっかり落とし込む必要があります。ベーシックを押さえることで、ベテランの先生は復習だけでなく新たな発見もしていただけるでしょうし、新米ドクターは盤石な土台を築くことができスムーズに次のステップへと進むことができると思います。
衛生士や歯科助手のスキルアップも必要

歯周外科処置のアシスタントは助手や衛生士が行うことが多いにもかかわらず、助手や衛生士に外科処置について教えるセミナーはありません。そのため私は参加対象を広げ、先生と一緒に助手や衛生士も参加できるようにしました。
助手や衛生士のアシスタントワークが向上するとドクターが気づかないところにも気づけるようになるなど、結果として医院全体の歯周外科処置のレベルアップが期待できます。また、普段助手と衛生士とのコミュニケーションを取る機会が少ないドクターからは、受講後にスタッフとの関係性が良好になったという話も聞きます。助手や衛生士も一緒に学べることはSBCの大きな特徴のひとつですからぜひ一緒に受講してみてください。
サイトをご覧のドクターへ

講義はわかりやすさを重視し、トーク中心やホワイトボードを使ってひたすら説明するようなものではなく、症例写真などをスライドで見せながらその補足として説明する形式を採っています。
スタディグループに堅いイメージを持たれているドクターも多いと思いますが、SBCは違います。インストラクターが一方的に教えるようなワンマン講義には絶対にしたくありません。気になることがあれば講義中でもどんどん質問してもらって結構ですし、インストラクターも解釈のズレを感じた場合は積極的に指摘します。わからないままにしてしまっては、教える意味も半減してしまいますので、きちんと理解してもらうことを大切にしています。
また、講義後には毎回必ず1時間ほどお酒を酌み交わしながら受講生とインストラクターが交流できる「スコッチアワー」という懇親会のようなイベントを開催しています。講義中に聞けなかったことをインストラクターに質問できますし、他の先生や助手・衛生士との情報交換も行えます。もちろん、講義後でも不明点があれば電話やメールでの相談にも乗ります。お金はいりませんし、迷惑だとも思いません。何かの縁があってきてもらうわけですし、教える立場としての責任がありますのでこのくらいのフォローは当然だと思っています。
歯周形成外科の知識・技術を磨きたい先生、助手や歯科衛生士とコミュニケーションを深めたい先生、わからないことはとことん追究したい先生は、ぜひSBCを受講してみてください。ご参加を心よりお待ちしています。一緒に日本の歯科界を盛り上げていきましょう。

フィリピン、セブ島にトラックと歯科医師を
送ろうプロジェクト
現在フィリピンのセブ島には台風30号(ヨランダ)の被災者がレイテ島のタクロバンから海軍の船で3000人以上避難して来ています。
避難所やタクロバンに物資を送るために現地法人ブルーコーラルの下釜宏氏が指揮を執り、自社のトラックやスタッフを動員して被災者に支援を行っています。
また、我々が避難所に往診に行く際にも避難所への案内とサポートを行っていただいています。
何トンもの物資を運んでいる為、トラックがそろそろ限界に来ています。
そこでトラックを提供することにより物資を運んだり現地のクリニックに人を運んだりといろいろな用途に使えると思います。中古で約20から30万ペソ。日本円で言うと46万から69万円だそうです。
また、日本から持って行くのは大変なので現地での歯ブラシなどの歯科用品の購入費に充てたいと考えています。
2013年11月9日にフィリピン中部レイテ島タクロバンに被害をもたらした台風ヨランダ。死者数は(約)3600人。また、被災者は1290万人に上った。フィリピンの人口は約9400万人で、被災者は全国民の約7人に1人に相当する。避難生活者も190万人に上った。
今回、我々が往診に訪れたフィリピン ヴィサヤ諸島セブ島には当初4つの避難所があり3000人以上の人々が避難生活を余儀なくされていたが親戚を伝って別の地区に移住したり故郷に帰ったりと現在では1カ所の避難所で200人がテント生活をしている。
-
被災当時の写真

-
セブ島での避難所

2014年2月7日金曜日、我々は連休を利用し東京から3名、大阪から2名の計5名(歯科医師4名、歯科衛生士1名)でセブ島に入った。日本では20年ぶりの大雪が最初に降った週である。
避難所の子供たちは避難所近くの学校に行っているという事もあり日曜日に往診に来てほしいと依頼があったため、到着翌日の土曜日に事前に集まった支援金で現地のダイビングショップ、Blue Coralの下釜宏氏とともに支援物資の調達に行った。今回残念ながらトラックの購入とまでは行かなかったが計10トン以上の支援物資を送ってきたトラックは修理を重ねながらも支援物資を運んでくれた。
2014年2月9日日曜日。下釜氏の援助でドライバーを含めたスタッフ数人そしてヴィサヤ語しか話せない子供の為に通訳も用意して頂いた。青井先生を除いて初めて往診する我々は緊張と不安の中、避難所に入った。そこでは到着を待っていたかの様に子供たちが列を作り出迎えてくれた。
歯科医師・歯科衛生士で参加した廣原善政先生、廣原真紀さんは子供達にブラッシングの大切さを伝える為、参加すると決まった2ヶ月前から手作り紙芝居を作製し日本から持参していた。
現地でも人気の日本アニメのキャラクターを使った紙芝居はクオリティーが高く子供達はもとより大人や現地のスタッフにも大盛況だった。その後検診を行い歯ブラシ、シュミテクト、(株)YDMと(株)マイクロテックから支援頂いたデンタルミラーを手渡した。(うがい用のコップはその時すっかり忘れていて渡し忘れたが後に連絡して配って頂きました。)
口腔内はカリエスの多さに非常に驚き私が診た限りではカリエスのない子供がいなかった。治療の供給が安定していない事や歯科教育が行き届いていない事も考えると子供たちの口腔内の将来は非常に心配である。到着日に空港で他のボランティアグループと話す機会があり数十年前からフィリピンでボランティア活動をしている事を知り考えさせられた。
今回のボランティアを経験して普段は最先端治療を勉強する事が歯科医療のすべてだと考えていたが、今まさに必要とされる最前線の現場で今一度、歯科医師としての本分を思い出すと共に自分の仕事の重要性を再認識した。
そして、タイトなスケジュールでしたが、日本で学科を勉強した事もあり全員がスキューバのライセンスを所得した事をご報告します。ライセンス所得なんてという思いもありましたが「心に余裕がない人にはボランティアは出来ない。精神的に辛くなるだけだから海にも出よう。」という青井先生の言葉が背中を押してくれました。
また、支援金を送って頂いた方にはTシャツを買いました。これは単にダイビングライセンスの所得やお土産ということではなく、現地に行き、現地で物を買うことで現地の景気上昇に貢献するだけでなく、フィリピン政府に税金が入り、最終的に被災地に支援金が回るということを目的としています。

避難所では普段の日本とはかけ離れた歯科事情に直面した。「そこにはインプラントや審美歯科はない」必要とされるのは日常の治療であり、それは阪神淡路大震災、東日本大震災、セブ島の被災地に一人往診に赴いた青井先生の言葉のままだった。今後起こるといわれている東海~南海での地震でも多くの被害がでると思われる。その時に歯科医療従事者がやれることをやる環境を整えておくことが必要ではないかと考えさせられた。
歯科医師法第一条にはこのように記されている。 “歯科医師は、歯科医療及び保健指導を掌ることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。”
これは資格を手にして与えられる歯科医師の使命だと思う。私たちは人を救うことを生業として選んだ人間だからだ。
最先端から最前線までの全てが歯科医療であり、我々はそれに携われる人間であるということを忘れずにいたいと思う。
最後に、このような機会を与えて下さった青井良太先生、現地での支援物資の購入、移動、案内やダイビングの指導までお世話になりましたヒロさん(下釜宏氏)をはじめ現地スタッフの方々、廣原善政先生、廣原真紀さんご夫妻、岩上朋代先生、支援金を送っていただいた方々、検診で使用したゴーグルを提供し届けてくださった大木先生夫妻に感謝の意を表します。
SBCアシスタントインストラクター 白井健太郎
よりオープンな勉強会「club SBC」
SBC事務局では、歯周形成外科コース「SBC(Surgical Basic Course)」の受講生・修了生を含めどなたでも参加可能な勉強会「club SBC」を開催しております。

club SBCはSBC受講生より受講後のフォローアップをしてほしいとの要望から発足した勉強会です。SBCで学んだ知識や技術の実践と検証、よりハイレベルな歯科医療の知識・技術などの情報交換、会員同士の活発な交流、各種学会や勉強会への積極的な参加を通して、医療を通じた社会貢献を目的としております。
開催はSBCの講習の前日の土曜日にオンラインで行っております。
より深い学び・気づきを得ていただける内容になっていますので、遠方の方も是非一緒に時間を共有できればと思います。
club SBC会長 宮地 栄介、
スタッフ一同
club SBCのご案内
| 会場 | Zoom開催 |
|---|---|
| 日時 | SBCコース前夜(土曜日)19:30~22:00 |
| 会費 | SBC第1.2回目コースの前夜:無料 第3回目の前夜特別講演当日:会費:4.400円(当該期の受講生は無料) |
| お申込 | SBC(Surgical Basic Course) 歯周形成外科コース 公式フェイスブック申し込みはこちらから ※開催詳細はこちらから随時アップデート致しますのでご確認下さい。 |
| 特別講演お申込 |
特別講演は下記よりお申込みください。 申し込みはこちらから |